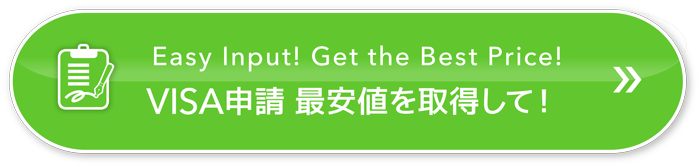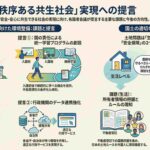日本政府( 出入国在留管理庁 )では、総合的な支援をコーディネートする人材の役割等の検討に資するため、幅広い関係者から意見等を聴取する関係者ヒアリングを実施しています。
参考:出入国在留管理庁
浜松市
令和4年11月15日開催
浜松市企画調整部国際課
公益財団法人浜松国際交流協会
活動概要
浜松国際交流協会
ワンストップ相談事業に関わるフルタイムの職員は、3名(うち、ブラジルにルーツを持つ職員2名)。それ以外に、各言語(スペイン語、フィリピノ語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、英語、日本語)で対面相談に対応するスポット相談員がいる。
令和3年度に受けた外国人からの多言語による生活相談の件数は、6,701 件。定住化が進んでいるため、相談内容は日本人と同様、また職業紹介事業も行っているため雇用・労働に関する相談が多く、その他福祉に関する内容等が多いが、外国人特有の「在留資格」や「日本語学習」についての相談もある。
コロナ禍以降、孤独を感じる高齢の外国人が増えている印象がある。本国に帰るつもりもなく、兄弟とも疎遠で、一人暮らしをしており、年金も多くもらえないような外国人の方は、将来に不安を感じるものの、身近に相談者がおらず、孤独を抱えやすい。
発生する問題の大半を、直接的に解決するのではなく、他機関へつなぐことで解決を図っている。DV問題が起きた際には警察署へ同行したり、具合が悪く医師の診察が必要なケースであれば診察に同行したりするなどしている。義務教育を終えた年齢の子どものケースで適切なつなぎ先が見つからないことがあった。NPOに依頼することもできたが、支払う謝金がなく、半分ボランティア前提になってしまう。
日本福祉大学名誉教授の石河先生の御協力を得て、平成 20 年からソーシャルワーク研修を開始した。
ソーシャルワーカーから、外国人への相談支援に当たり何に気を付けたらよいかという相談を受けることもある。出入国在留管理庁が検討している「総合的な支援をコーディネートする人材」(「コーディネーター」)には、日本社会の制度そのものはもちろんだが、外国人特有の在留資格に関しても、そのケースをどこにつなぐべきか判断できるくらいの知識が必要と考える。例えば、本人が難民と言ったときに、難民申請中で滞在している人と認定されて滞在している人の両方がいるため、その状況に合わせて対応する必要があるということを知識として持っておくことが重要。
外国人と日本人の文化の違いを理解できる力が必要である。また、宗教的な言い回しが原因で外国人と日本人との間でトラブルになったケースもあり、宗教的な感覚の違いをくみ取る力が必要であると思う。必ずしも差別とはいえないようなケースであっても、外国人であるから差別をされていると感じている方もいるため、そうしたことに対する理解が必要である。
コーディネーターになるのに必要な実務経験としては、行政に関わる業務に携わったことがあるかという点や、外国人の方々を全体的に支援する立場にあったことがあるかという点が考えられる。
面接技術等について、経験だけだと経験が間違っている場合もあり、そのときに自分の経験があるから、こっちの方がよい、こっちの方が正しいという思い込みで対応してしまうことがある。さらに、それが変な自信になってしまうと後からの修正が難しい。そういう意味で、こうやるのが一般的、こうした方がよいという知識は必ず必要だと思う。
浜松市における予防的支援
新しく住民登録した外国人の方々に対して、当市での生活に必要な情報をまとめた「ウェルカムパック」(7言語)を住民登録の窓口で必ず渡す。単に渡すのみという状況になっており、外国人本人に自主的に読んでいただく形になっている点が課題である。
市の窓口には通訳職員が 3、40 名いるが、これらの職員を対象に、毎年、外部から講師を招き国際交流協会職員との合同研修を実施している。
市では、以前から外国人を支援する人材の待遇に係る課題(専門職をどう確保してできるだけ長く勤めていただくか)に直面していた。そこで、現在は、多文化共生に係る(国の)資格がないため、民間団体等が行っている研修等を受講してもらい、それに応じて処遇を上げることを財政当局に認めてもらい、現在3年間計画で処遇向上に取り組んでいる。コーディネーター制度については、ソーシャルワーカーのような方を国家資格化して、公的な認定を与えるようにしてもらいたい。そうすれば、財源確保しやすくなり、専門性の高い人材を確実に確保でき、経験やノウハウがより蓄積されることにつながるのではないかと思う。
ワンストップセンターで外国人を支援するソーシャルワーカーのような人材を配置必須とするような仕組みを作ってもいいのでは。
栃木県
令和4年11月17日開催
公益財団法人栃木県国際交流協会
栃木県国際交流協会概要
栃木県国際交流協会が運営する「とちぎ外国人相談サポートセンター」(「サポートセンター」)には、外国人の相談員が 11 名おり、そのうち2名が非常勤の嘱託職員である。また、相談員のヘルプに入っているプロパー職員が3名程度いる。
相談員間で経験や能力に差がある点が課題である。この点については、相談員間で情報交換を行い、埋めるようにしている。
外国人からは、在留資格の変更や更新といった入管手続、離婚やDV、雇用関係、医療関係、通訳・翻訳依頼など、幅広い相談を受けている。
平易な相談と複雑・複合的な相談の切り分けは行っていない。対応の流れとしては、まず各言語の相談員が相談を受けて、対応困難な場合には、別の相談員が助言したり、必要に応じて関係機関に問合せを行ったりしている。
受け皿となる連携先を拡充するために、専門機関や他の相談窓口と情報交換を行っている。
出入国在留管理庁が実施する研修へ参加してもらっているほか、相談員向けの実務研修会を実施している。当会の相談窓口の業務は、情報提供が中心であるので、専門的な知識を深く身に付けるよりも、幅広い知識を浅く広く身に付けることに重きを置いている。
当会では、県内の相談窓口の相談員向けの相談員研修会、県内の通訳者・翻訳者を対象とした研修会等も開催している。
栃木県国際交流協会が配置している「外国人材コーディネーター」
当会では、独自の取組として、企業等における外国人材の受入れ体制整備を支援する「外国人材コーディネーター」を配置し、「外国人を雇用したいがどこから手をつけてよいか分からない」などといった悩みを持つ企業からの相談を受け、弁護士や社会保険労務士につないだり、外国人を雇用した後の相談に応じたりしている。
現在、「外国人材コーディネーター」は1名いる。いわゆる有期雇用職員であり、1年ごとの契約で、最長5年間の契約期間である。また、資格の要件はなく、採用時に経験を確認する形としている。
以前、当会において、多文化の視点、ソーシャルワークの視点で外国人からの相談に対応できる人材を育てようということで、数年にわたって県からの委託事業として研修を実施していたことがあり、そこで出てきた課題がある。
一つ目は、同研修は、専門的な知識、たとえば、教育、社会福祉、人権、労働関係等について幅広く学ぶ内容としていたが、職場に戻ったときに、その職域や職位の中でどの程度実践できるか、限界があった。研修を受けた相談員もいたが、制度の壁があり、今はいない。長く続けられる(形での)人材確保が一番良い。
二つ目は、言葉が通じないと相談はうまくいかないが、多文化ソーシャルワーカーになった人も、自分ができる言語であればいいが、できない言語に対応する際には、その都度通訳者が入らなければならず、ランニングコストがかかってしまうという課題もあった。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
- 幅広い相談に対応できることが前提になると思う。
- まずは、モデル地区などで試行し、様子を見るという方法もある。既存の人材に求める役割を増やすとなると、負担が大きくなってしまうので、現場の相談業務を滞らせない形でお願いしたい。
- 専門家の方に外国人の支援の視点を身に付けてもらい、コーディネーターになってもらう形もありではないか。
- 想定されている「総合的な支援をコーディネートする人材」は、専門家だと思うので、例えば自治体の窓口だけでなく行政書士会の中にも置くと良いかもしれないと思う。
- 外国人の方が、直接、専門家につながることのできるような体制があればいいと思う。また、専門機関同士の横のつながりが非常に重要。つながりがあれば問題も解決しやすくなるし、見えない問題も共有できる。専門機関をつなぐ
- キーパーソンのような人材や専門機関の横のつながりを強化するような窓口を作ってもいいのではないか。
愛知県
令和4年11月17日開催
愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室
公益財団法人愛知県国際交流協会
愛知県国際交流協会 活動概要
愛知県国際交流協会の相談窓口「あいち多文化共生センター」の相談員は全部で6名おり、全員が同じ「多文化ソーシャルワーカー」という職名である(うち社会福祉士資格保有者は2名)。相談の全てを多文化ソーシャルワーカーが対応している。多文化ソーシャルワーカーは、生活に困窮している方や障害を抱えている方等、様々な外国人の方を対象に、窓口で相談に応じるとともに、複雑な問題については専門機関と連携し、解決に向けて継続的に支援を行う。必要に応じて、公的機関の手続に同行したりもしている。また、県内の市町村や他の相談機関からの対応方法に関する問い合わせや、協力要請にも随時応じている。
多文化ソーシャルワーカーは、原則5年間の嘱託職員という形で契約している。県庁全体で、人員が減っている状況で、正規職員として配置するのはハードルが高い。募集の枠は、社会福祉枠と言語枠の2つがある。社会福祉枠の場合、社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者であることと、外国人相談対応の経験があることなどを条件とし、社会福祉の知識を活用した筆記試験を課している。また、言語枠の場合は、採用試験の際に、外国人相談対応の経験と語学力を条件とするが、語学に関する資格は必須とせず、言語の試験により語学力を判断している。
当会における令和3年の相談件数 3,801 件のうち、多文化ソーシャルワーカーが対応したものは 3,683 件。
日本語を勉強したいという外国人の方に対して日本語教室を案内しているが、その際、重視するのは「通いやすさ」である。また、可能な範囲で、学習目的に応じた教室案内を行っている。日本語能力のレベルチェックは実施していない。
愛知県国際交流協会 活動概要
愛知県多文化共生推進室では、地域日本語教育も担当している。地域の日本語教室の取組を促進しており、外国人学習者の日本語能力のレベルチェックを目的とした評価シートの作成についても検討している。外国人の方が地域住民の方と一緒になって日本語を勉強し、コミュニケーションを取りながら、地域に入り込んでいくことを目指している。そういった方針もあり、文化庁の「つなひろ」を始めとするオンライン教材は基本的には使用していないが、日本語教室へ通う時間や手段がないといった方には必要に応じて紹介している。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
「総合的な支援をコーディネートする人材」については、外国の制度や法律に詳しく、言語ができる方が最適であると考える。また、コーディネーターにはその地域のことをよく分かっている方になっていただくのが望ましいと思う。
研修のカリキュラムは、その地域に合った内容にするのが一番良いが、地域によっては有識者等のリソースがなく、仮に補助金が出たとしても独自のカリキュラムを策定したり、研修を実施したりすることが難しい、ということがあるかもしれない。
外国人の方に対して相談支援を行う際には、聞き取りをしっかり行い、相手の言うことを正しく理解した上で、相手が置かれている状況を一緒に整理する、といったことが必要であり、これらの基本的なところを学ぶ必要がある。
コーディネーターの方々に対し、専門知識に見合った給料や安定した職、しっかりとした身分保障を与えることができる体制を構築できるよう、財政的援助や雇用した機関への助成金の支給等の仕組みを作ってほしい。
大泉町
令和4年11月22日開催
群馬県大泉町企画部多文化協働課
大泉町 概要
大泉町では、税や転出入に関する部署等に通訳を配置し、外国人からの相談に対応している。これらの部署で解決できない場合は、(一元的相談窓口を運営している)多文化協働課に在籍している通訳者が、長年の経験に基づいて、関係機関とのつなぎを行い、事案の解決につなげている。
相談内容は、税金、出産、子育て、最近であればコロナに関するものが多い。「日本語を学びたい」という相談が月に 10 件程度あるが、こういった相談に対しては、交流協会が行っている日本語教室を案内している。
相談内容の難易度に応じた業務の切り分けは行っていない。来庁者に対しては、まず総合案内で相談内容を聴取し、その後担当部署につないでいる。簡単な相談内容であればその場で回答できるが、法的な問題が絡むものは、関係機関へヒアリングするなど調べてから回答しているので、日数を要するものもある。
大泉町で対応困難なものは、警察や県、国際交流協会等の機関につないでいる。受け皿となる連携先を拡充するために、県主催の日本語教室のミーティングに参加して意見交換をしたり、近隣の市主催の防災訓練に参加したりして、地域の関係機関との連携を強化している。つなぎ先の確保が難しいのは、法的な部分から漏れているケースである。NPO団体もすべて対応できる訳ではないが、生命や個人の生活を維持するために、(公的機関が支援できない部分を、NPO団体が)なんとか支援してくれているというのが実情。
多文化協働課の通訳者は、NPO団体とつながったり、研修等のあらゆる機会に顔を出したりして日頃から顔つなぎを行っており、何かあった際に協力してもらえるような関係作りをしている。各国の色々なグループのキーパーソンとつながっており、(キーパーソンを通じた)情報発信を行っている。ボランティアグループと協働して事業をやったり、警察署主催で外国人の方を集めて道路清掃や防犯パトロールも行うこともある。高崎健康福祉大学と連携して、外国人学校の生徒を対象にした保健講座等を行っている。
大泉町における予防的支援
外国人の集まる場所、例えば移動領事館、日本語教室、外国人学校の保護者会、進路説明会、各国の人が母国の人向けに開催するイベント等に出向いて、町に関する情報提供を行っている。以前は、外国人を集めて実施していたが、なかなか集まらない状況だったので、こちらから出向くようにした。
転入してきた外国人に対して、自治会の仕組み等の生活に必要な情報を文書でまとめた「転入セット」を渡している。
日系ブラジル人が多く、日本語能力が十分でない人もいるため、日本の制度やマナーを理解してもらい、母国語でもいいので周りの人に伝えてもらう「文化の通訳」登録制度という取組を行っている。この取組は、メールアドレスを登録してもらっている方に災害情報等の町からのお知らせを配信し、その情報を受け取った方から身近な人に発信してもらい、情報の拡散を図るものである。現在、約 700 人の方が登録している。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
- 幅広い知識をもっていないとつなぎ先はなかなか分からない。また、経験も重要。我々は行政職員として人事異動で色々な部署を回っているので、(どの部署がどのようなことをやっているかをある程度把握できており)なんとかつなげているが、経験がないと適切なつなぎは難しいと思う。
- コーディネーターに必要な知識は、外国人が生活する上で必要なことすべてということになると思う。
- 地域によって資源が違うので、(同じコーディネーターであっても)地域によってできることとできないことが出てくる。例えば、多言語対応、NPO、医療機関等の資源は集住地域の方が進んでいる。ただ、外国人が少ないから対応不要とはならないので難しい部分である。
- 国家資格化について、資格はないよりもあった方がいいが、資格を持っているからできる、実務に移せるという訳ではない。経験に裏打ちされたものが必要である。
- 行政窓口においては、タイムリーな対応が求められる場面がある。すごく困っている方が窓口に来た場合に「今からコーディネーターに連絡を取るので、今日は対応できません」という対応では難しい局面もあるので、その辺りを解消する方法として、オンラインでの対応も含めた検討が必要だと思う。
- 生死に関わるような場面では、他機関との連携を行っている場合ではないこともあるので、コーディネーターが受入れ先等と直接調整できるような体制を取れるようにした方がよい。
仙台市
令和4年11月22日開催
公益財団法人仙台観光国際協会
仙台観光国際協会 概要
仙台観光国際協会において相談対応を担当している部署(「多文化共生センター」)には7名の職員がおり、そのうち2名が正職員、5名が嘱託職員である。実際に窓口で相談対応に従事しているのは、係長を除く6名。
最初に相談を受けた者がその後もなるべく対応していくが、土日も窓口を開けておりシフト制で対応しているので、6名で共有しながら対応している。
相談員一人ひとりが、通訳を使うかどうか、関係機関にどのように連絡をとるか、いつまで寄り添うか、(他機関にケースを引き渡した後も)どこまでフォローアップするかといったことを考えて対応している。
採用時に求めているものは、外国語の能力と運転免許ぐらいである。また、社会福祉士の資格は所有していればプラスアルファになると思う。相談員の中には自主的に社会福祉士を取得している者もいる。
職員の待遇が一番の課題である。募集をかけると人気は高いが、雇用形態が不安定、雇用期間が限られているといった課題がある。
生活全般にわたる相談を受けている。内容によっては、寄り添い型で何年も続くような支援もあり、対応にかなりのスキルや経験年数を要するものある。当事者間で裁判が続いているケース、児童相談所に保護されているケースもある。複雑な相談がとても増えている印象があり、割合としては全体の1、2割程度を占めていると思う。特に、令和元年度に専門相談会(地方入管局、弁護士、行政書士、労働局、税理士と連携してそれぞれ月1回又は2、3か月に1回程度開催)を始めてから重い相談が増えてきた。
「日本語を学びたい」という相談は上位にくる。市民団体や学習支援団体との連絡会議の開催や日本語学習関係の情報を集約しHPで掲載するなどしている。(相談対応部署とは別の部署に)日本語学習支援の担当が二人おり、相談者のニーズに応じて、クラスに入ってもらうのか、マンツーマンのレッスンにするのか、オンラインがいいのか等の提案をして、学習につながるまでのサポートをしている。
仙台まで来ないと日本語教室がない、仙台にしか領事館がないといったケースについては、市外に住む方でもサポートしている。また、同じ国の人やコミュニティに知られたくないとして、隣県から当会に相談してくる人もいる。おそらく、自分が住む地域に相談できる人もいないのではないかと思う。定期的に自治会の役員会のような場に赴き、民生委員や児童委員に対して、外国人住民の方がいたら当会へ様子を知らせてもらうよう働き掛けをしている。
他の地域の自治体の窓口に行かないと解決できない場合には、県の国際交流協会につなぎ、市町村と連携してもらうこともある。また、大使館で申請をしなければならない、市内では医療通訳に対応できないなど、仙台で対応できないような相談については、全国を探して他団体を紹介することもある。
他機関連携については、専門機関から助言を得る場合もあるが、主に行政機関の担当課へつなぐことで対応している。連携先を拡充するためにやっていることとして、外国人住民と関わりを持つ部署と一年に一度情報交換会を開催しているほか、外部の研修会等に参加した際に新たな連携先になりそうな団体がいたら、積極的に連絡をとるようにしている。「外国人相談窓口ネットワーク」というネットワークを構築しており、研修会の実施や情報共有をやっていた。実際に、このネットワークを活用して他機関につないだこともあった。
各機関の対応できる範囲では互いにカバーし合えず、支援の隙間に落ちてしまうようなケースもある。そういう場合には、コミュニティのリーダーの方やNPO、教会等の助けを借りることもある。行政の隙間に落ちるような部分は、最後は人の情にすがって連携するしかない場面もある。
国際活動団体の登録制度を行っており、コミュニティ団体の代表等の連絡先等については、ある程度把握している。現在約 150 団体が登録しており、その情報はHPで公開している。毎年更新しており、相談の中で役立っている。
仙台観光国際協会の予防的支援
出前型のオリエンテーションを積極的に実施している。仙台には留学生が多いところ、日本語学校や専門学校、大学に資料を配布して案内している。通訳人や資料等も当会で全て準備するので、負担のない形で利用いただいている。監理団体から実施の要望があることもある。
オリエンテーションでは、交通ルール、ごみ出し、近隣トラブル、防災、情報収集の方法等、主に相談窓口で苦情として受け付ける内容を扱っている。外国人のスタッフも同伴して対応するようにしており、同じ国の人の立場から話をするようにしている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
- 行政の側に配置してくれると良いと思う。想定されている「総合的な支援をコーディネートする人材」が市役所等にいてくれれば、当会とのつなぎ役としても期待できるし、役所内で見過ごされてしまうような案件に気付いてもらえるかもしれない。
- 当該人材が日本語学校に出向いて、オリエンテーションが行われているかをチェックしたり、オリエンテーションを実施したりするのも良いかもしれない。経験上、オリエンテーションの実施を依頼してくる学校は問題が少ないので、その実施を外部に頼むような状況にない学校を対象にすると良いのではないか。
- 正職員には異動があり、嘱託職員は有期雇用なので、人材を育ててもその人の経験を生かせないことが我々のような協会の一番の課題である。「総合的な支援をコーディネートする人材」についても、定期の異動がある職員を育てるのか、それとも年数が限られていたとしても嘱託職員を育てるのかという点が悩ましいと感じる。
- 今いる職員が研修を受けて認定をもらえるような仕組みであれば、外部の関係機関とコンタクトをとる際にすごく良いと思う。また、この分野で働く職員は、海外で生活したことがある人や何かに貢献したいという気持ちを持って働いている人が多いように思うので、認証制度によって少しでも自分の能力に自信が持てるようになれば良いと思うし、(有期雇用の場合には)次の就職のときに今の経験を生かせるような制度にしてくれると有難い。
- 専門性の観点から国家資格化は必要だと思う。国家資格化が難しければ認証という形でもよいし、研修を受けてもらう方法もいいと思う。
- コーディネーターに求められるのは、能力もさることながら、忍耐力が重要であると考えている。相談の場面では忍耐力が問われるケースも多い。
横浜市
令和4年12月16日開催
横浜市国際局国際政策部政策総務課
公益財団法人横浜市国際交流協会
横浜市国際交流協会 概要
横浜市国際交流協会が運営する「多文化共生総合相談センター」(「相談センター」)では、現在月曜日から金曜日の10 時から 16 時半までの間、13 言語で相談を受け付けており、1日当たり3~5人の相談員体制で対応している。地域に「国際交流ラウンジ」(「ラウンジ」)が設置されており(現在 18 区のうち 11 区に設置)、そちらにも相談窓口が設置されているところ、当会では3つのラウンジを運営している。
相談員は専任職員だが、無期雇用の人も一定数いる。人材が集まりにくい言語があり、中国語や英語は割と集まるが、ネパール語、ベトナム語、タイ語、タガログ語は集まらない。通訳ボランティアも同じ状況である。
日本語学習に関する相談が圧倒的に多く、そのほか教育や行政手続等、いわゆる生活上の相談が多い。労働に関する相談もある。
窓口の相談員は長く働いている者が多く、経験・スキルがあるベテランが多いため、行政につながなければならない相談(DV等)以外は基本的に相談員が連携団体につなぐほか、対応困難な場合には職員も入り対応している。相談記録の共有を行うことで、どの相談員でも同じような対応ができるようにしている。
連携団体につなぐなどしているので、全く対応できないということはほとんどない。すぐに答えられない複雑な相談については、折り返しで対応するなど確実な情報をお伝えするようにしているほか、当会のみで解決に導くことができない案件のうち法律相談や労働相談、ビザに関する相談については専門機関につなぐようにしている。また、つなぎ先で通訳がつかず、相談が途切れることがないように、通訳ボランティアをつけてつなぐようにしている。
専門機関には回せないが、少し時間のかかる相談も多い。たとえば「子どもを呼び寄せたい」や「学校はどうしたらいいのか」といった相談は、相談があってからお子さんが来所するまでに時間が空いたり、学校を訪問する場合に通訳を付けたりすることもあり、時間がかかることもある。
横浜市の特徴として、様々な外国人支援に関するNPO・NGOがあるので、そういった団体との連携・協力体制をとっている。
ラウンジにおいて、月に1回、教育相談やビザの相談、法律相談等の定例相談を行っているほか、相談センターでも不定期だが弁護士相談や行政書士相談を行っている。
横浜市国際交流協会の予防的支援
外国につながりのある生徒の数が6割弱を占める学校で、その親を対象にゴミの出し方等生活上のルールをガイダンスするなどしている。日本のルール等について知ってもらうためのガイダンスをタブレットで視聴してもらう取組をする。外国人住民の孤立防止を重視している。地域に参画してもらうため、地域のイベント(お祭り、防災訓練等)の情報をお知らせするとともに、相談員も通訳兼橋渡し役として一緒に参加するなどして、地域と外国人住民をつなごうとしている。
ラウンジに来ることができない外国人への情報提供をどうすべきかが課題だ。アウトリーチが必要と思っており、教会や集住地域の学校に赴き説明会を開催することや、SNSを活用した情報発信を行っていくことを考えている。
こどもは苦労しながらも学校生活において日本の文化、ルールに触れていくので、こどもを通じてラウンジに来ない親にアプローチしてルールを伝えていくのも一つの方法だと考えている。なお、支援されていたこども達が支援する側になってくれる例もあり、たとえば、「中区外国人中学生学習支援教室」のサポーターの半分は同教室のOBである。
LINEやFacebook等での生活情報発信、LINEでの相談対応もしている。また、地域日本語教育の事業においては、横浜の情報や生活情報を提供するようにしており、そこで相談センターの周知を行うようにしている。コロナ禍でオンラインによる日本語教室の開催が活発になり、今までつながっていなかった方ともつながれるようになったというメリットはある。
かながわ国際交流財団の「外国人住民のための子育て支援サイト」のように、出産前からつながっていくためのアプローチや色々な資料の作成というのも非常に重要だと感じている。
地域日本語教育の事業においては、企業へのアプローチとして、業界団体に対してメーリングリスト等で当協会や当協会が受託運営する多文化共生総合相談センター、にほんご学習支援センターの存在等を雇用者側にもお知らせし、適宜必要な時にアクセスしてもらえるように心掛けている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
- 相談支援に関する部分に役割を絞って考えた場合、窓口の相談員と同じ経験をしてきて、色々な事例や制度について知悉しており、適切なつなぎ先やどこまで相談に立ち入るかの線引き等をできることが必要だと思う。また、当事者性や外国人の価値観を理解し、ソーシャルワークやカウンセリング等、相談援助の最低限の知識やスキルを持っている必要がある。それらについて、研修を通して一度体系的に学ぶことで、スーパーバイザーの役割を担いやすくなると思う。そのプログラムを作る際には、専門家はもちろん、現場の実践者や当事者として相談対応に当たってきた方をメンバーに入れていただき、カルチュラルコンピテンス(多文化対応力)も視野に入れて整理を行うのがいいと思う。
- 相談者と連携先を最短でつなぐという点は、一人のコーディネーターで対応できるものではなく、複数名によるペアやチーム体制ではないと難しいと感じている。多言語に対応できるコーディネーターやソーシャルワーカーのような相談援助の専門性を有する者が複数名体制で対応するというのが望ましいと思う。その上で、連携先とのネットワークづくりや外部との勉強会が定期的にあることで、何かあったときに連絡しやすい関係ができると思う。
- 色々と悩まれた結果、相談先が分からず帰国されてしまう外国人の方もいる。まだまだ知られていない相談窓口について知ってもらう必要があるし、予防的支援と相談対応は重要だと思う。
- 横浜市の場合、中小企業やまち工場も多く、日本語教育や相談対応に係る専門人材の配置が難しいことも多いと思う。地域日本語教育の取組の中で、外国人従業員向け日本語教室のプログラムで企業及び従業員とつながっていたことにより、何かあった際に相談へとつながった。
- 横浜市は規模が大きいので単独でできる部分もあるが、自治体によっては、相談対応が十分にできない場合もあると思う。近隣市町村での連合的な形による支援体制づくりもあり得るかもしれない。
- 地域レベルでつながり、様々な課題に取り組んでいくことが重要と考えており、そういった意味で、コーディネーターには、アウトリーチやコミュニティワーク等の視点を持って地域で活動できる人、コーディネーションやネットワーキング、ファシリテーションを行うことができる人が望ましく、より支援にも深みが出るのかなと感じている。
- 国家資格化は、今の段階では時期尚早なのではと感じている。コーディネーターの専門性は一つである必要はなく、多様な専門性や経験を持った方が関わることで多文化の領域がより豊かになり、結果支援が円滑になる部分もあると思う。まずは、各領域の様々な国家資格・専門資格の専門性の中にどれだけ多文化の視点・プログラムを入れていけるのかが先ではないかと感じている。その後、多文化に関わる相談支援に必要な要素が可視化され整理されていく中で、国家資格化の具体的な意義と内容が見えてくるのかなと感じている。
武蔵大学
令和4年12月21日開催
武蔵大学教授 アンジェロ・イシ 氏
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
どのエスニックコミュニティにも人が一斉に集まるイベントがある。趣旨を説明すれば賛同してくれる可能性が高いので、そこにブースを設けさせてもらう、時間を確保してもらうことが良いと思う。イベントで具体的な相談に乗ることは難しいと思うが、出向くこと自体がコーディネーターという新たな制度のPRにつながる。在日ブラジル人を例に取れば、各総領事館が定期的に移動領事館を開催したり、教育フェアを開催したりしているので、コーディネーターがそういったところに行くことも考えられる。
在日ブラジル人の例を挙げると、人材派遣業者の事務所に人が一番集まるところ、そこで悪質な業者にだまされるケースもあるし、だますとまではいかなくても、人材派遣業者が外国人に対して最も知っておくべき知識を与えない場合も多い。代々木公園でブラジルフェスティバル的なイベントが開催されており、多くのブラジル人が集まるので、そこにブースを設けることも一案である。その他の配置先として、各国の大使館、領事館を考えてもいいと思う。大使館等によっては、コミュニティ支援担当の部署やキーパーソンを決めている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に求められる能力について、語学力を強調したい。日本語のみを使用する優秀なコーディネーターも良いが、理想は最低でも英語ができるバイリンガル、もっと言えば英語以外の言語ができるバイリンガル、トリリンガルが一番有難い。
外国人の主要な出身国に関する知識の蓄積と理解が必要だと思う。在留資格が同じでも国籍あるいは出身地が違えば、まるで違うニーズや感覚を持ち、異なる状況にあり、共通点よりも異なる部分の方が多いというケースもある。異文化理解に限らない、政治状況や社会情勢、それぞれの国での階級・階層がどうなっているのかといったことを含めた各国の幅広い知識、情報の蓄積、理解が必要である。
国家資格になる方が目立つ、箔がつくということで、より優秀な人材が集まるというメリットがあるので、国家資格化を推したい。
コロナだけが原因とは断定できないが、この数年間で確実に日本に住む外国人には、孤独・孤立という問題が大きくなっている実感がある。間違いなく社会問題になりつつあるので、この問題に注目することには十分な意義がある。
多文化社会専門職
令和4年12月22日開催
一般社団法人多文化社会専門職機構 菊池 哲佳 氏
多文化社会専門職機構(TaSSK) 概要
多文化社会専門職機構(TaSSK)は、多文化社会の問題解決に取り組む実践者や研究者が学びとネットワークの場を形成し、多文化社会の問題解決に貢献する専門職の認定事業を行うことを目的として始まった組織であり、現在の会員は 50 名となっている。東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターのコーディネーター研究会やコミュニティ通訳研究会、日弁連の外国人法律相談における通訳人の制度に関する研究の有志が呼び掛けて始まった。
主に三つの事業を柱として行っている。そのうちの一つが多文化社会専門職認定事業であり、認定事業の一つとして、多文化社会コーディネーター認定プログラムを実施している。現在の認定者は9名。
多文化社会コーディネーターは、「あらゆる組織において多様な人々との対話、共感、実践を引き出しつつ、参加、協働、創造の問題解決へのプロセスをデザインしながら、言語、文化の違いを超えて、全ての人が共に生きることのできる社会に向けて、プログラム(市民活動、国際交流協会等の事業、自治体の施策等)を展開、推進する専門職」と定義している。
多文化社会コーディネーターの実践領域は、行政、教育、福祉、医療などの様々な領域がある。その中で、コーディネーターはそれぞれの専門分野で実践することを想定している。
コーディネーターの認定だけではなく、研究や養成も行っている。これが二つ目の柱として行っている実践研究事業となる。
三つ目の柱として社会発信事業を行っており、多文化社会実践研究フォーラムを毎年行っている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
多文化社会コーディネーターが他のコーディネーターと異なる点は、公共政策に関わる点であると考えている。
コーディネーターは、現場の問題状況を俯瞰的に捉えて、人や組織をつなぐという役割を担う。現場に密着したコーディネーターの必要性を感じている。
ている。
総合的な支援をコーディネートする人材について、外国人相談事業におけるコーディネーターの役割が参考になるのではないか。外国人相談事業で重要なことは、外国人が抱える問題を相談者に代わって解決してあげることではなく、相談者自身が自分で解決できるようにサポートすることや、エンパワーメントしていくことであると思う。
多文化社会に関する基礎的な知識や制度の理解が求められる。例えば、在留資格に関する知識は当然必要だろう。また、連携・協働を推進していくにあたっての、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力、デザイン・プログラム能力も求められるだろう。また、地域社会に関する知識のほか、自身がコーディネーターとして精通する専門領域が一つあることも役割を果たす上で大きいと思われる。しかし、最も重要なことは問題解決に向けて課題を設定する力であると思う。
ヤマウラ
令和4年12月23日開催
山浦 育子 氏
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
大学を卒業したばかりで、人生経験が少ない方は、いくら言葉ができたとしても相談対応は難しい。経験上、若い方は相談内容によってメンタルをやられてしまうことがある。また、言語については、外国人の場合はN1の日本語能力が必要である。日本人の場合は、たとえばTOEICで何点以上必要ということを事前に設定しておくといいかもしれない。
必要な専門性としては、知識面では言語と相談に関する知識があると思う。また、相談に関する経験も必要であるし、地域のことも理解していないと難しい。地域の国際交流協会が外国人住民とつながっていて、地域の状況を把握しているので、そこに聞くとよいかもしれない。
相談内容は複雑化してきている。離婚や子どもの教育等が複雑に絡んでいる相談において、「総合的な支援をコーディネートする人材」には、在留資格はここ、子どもの教育はここ、という交通整理の能力が求められる。
参考になる取組として、東京都つながり創生財団が実施している「外国人のためのリレー専門家相談会」がある。まず通訳者が相談者からヒアリングをし、内容をコーディネーターに伝え、その内容を踏まえてコーディネーターが専門家につなぐという形になっている。相談者から直接ヒアリングを行うことを想定している「総合的な支援をコーディネートする人材」とはその点で異なっている。
今後、入管庁が「総合的な支援をコーディネートする人材」を国家資格のような形で認定することになればとても有り難い。国家資格になれば、当該人材が現場に入りやすく、現場の方と連携し、一緒に取り組むことになると思う。
神奈川県
令和4年12月26日開催
神奈川県教育委員会子ども教育支援課
神奈川県におけるスクールソーシャルワーカー 概要
子ども教育支援課では、神奈川県内の政令市、中核市を除く市町村立の小・中学校にスクールソーシャルワーカーを派遣している。具体的には、県が県内4地区の教育事務所に50名を配置し、教育事務所が各市町村に派遣する形となっている。また、市区町村によっては、独自にスクールソーシャルワーカーを雇用しているところもある。なお、別の課の担当になるが、県立高校や県立特別支援学校にもスクールソーシャルワーカーは配置されている。
スクールソーシャルワーカーの資格要件として、社会福祉士と精神保健福祉士を示しているが、学校や福祉の現場での業務経験があれば、必ずしもこれらの資格を有していなくても採用することにしている。
スクールソーシャルワーカーは児童・生徒の置かれている環境をアセスメントして支援につなげていく。基本的には学校だけで抱えこまないで、関係機関と連携し対応している。連携先は、福祉関係や警察関係、医療機関や療育相談センター等、ケースによって様々である。また、以前は地域によって通訳がいないことが問題になっていたが、今はオンライン通訳も活用しながら対応できている。
外国につながりのある小学生が相談するとなると、まずは担任の教員や国際教室(後記)の担当教員、保健室にいる養護教諭ということが多い。
県において、初採用のスクールソーシャルワーカーに対して新年度前の3月に2時間程度の集合研修を実施し、県の職員として勤務するに当たっての必要事項等について研修を行っているほか、年に4回、スクールソーシャルワーカーの会議を開き、その中で各回4時間程度の研修を行っている。また、教育事務所では、地域特性に応じた事例検討会等を各回4時間程度開催している。
外国につながりのある児童・生徒に特化した研修は行っていないが、昨年度の県の研修では、在留資格について情報提供を行った。
文科省の調査において、外国籍児童に係る案件についての項目がないため、具体的な件数は把握していないが、事例報告という形で外国籍の子どもに関する事例が一定数上がってきている。保護者の日本語能力が十分でないために、公的なサービスをなかなか利用できずに経済的に困窮しているケースがある。保護者が日本の文化とは違う文化を有しており、学校へ通うことに対する価値観も異なっているため、不登校になってしまう生徒もいる。生徒の方でも、親と交わす言語と学校で使用する言語が違うといった悩みがあり、学校に足が向かずに不登校になってしまうこともある。
外国籍児童やその保護者に対するオリエンテーションについては、自治体によって様々である。たとえば、自治体と学校が連携して、就学手続の際にオリエンテーションを実施しているところもあり、保護者にとって分かりやすいといった声がある。
神奈川県では、日本語指導が必要な外国籍児童が5名以上在籍している小学校や中学校に、「国際教室」を設置している。当該児童が5名以上 20 名未満在籍していれば教員1名、20 名以上であれば教員2名を配置し、勉強や生活の支援を行っている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
「総合的な支援をコーディネートする人材」を学校に配置する場合、学校という特殊な世界に入っていくことになるので、そういった環境で柔軟に人間関係を構築できる人間性が重要になると思う。また、同じスクールソーシャルワーカーが何年も同じ場所にいる訳ではなく、四六時中いる訳でもないので、自分だけで完結させずに支援を続けていくために、記録をしっかり残して引継ぎをしていけるような資料作成能力や情報を発信する力も重要になると思う。
国家資格化することにより、そういった仕事の地位や権利、労働環境が向上することで、支援に関わる人が増えることにつながるとよい。
ベトナム
令和5年1月25日開催
一般社団法人在日ベトナム共済会 山本 美香 氏
活動概要
相談者が、日本語を話すことができる場合は日本人の職員が、ベトナム語しか話すことができない場合は私が相談内容を把握した上で、一般社団法人在日ベトナム共済会の中で色々な人が関わり合いながら解決策を検討している。
相談内容については様々であるが、就労ビザや転職関係の相談が多い。そのほかには、家庭内暴力や夫が亡くなった場合の手続、銀行での手続、弁護士や産婦人科の検索方法といった相談も寄せられている。
共済会は、困っている人たちがより良い生活ができるようにという気持ちを持ってボランティアで活動を始めたものであり、活動資金等の支援は受けていないため活動が難しい面もある。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
困りごとがあって相談したいが時間が無いという方のために、オンラインで相談できるようにすると良いと考える。
コーディネーターは、色々な知識を持った方になってもらうのが一番良いが、そのような人材を育成するのは簡単ではない。寄せられた相談に対して時間を掛けずにすぐに対応できるよう、知識や経験をたくさん積んでもらいたい。
多言語センターFACIL
令和5年1月26日開催
NPO法人多言語センターFACIL 兼 武庫川女子大学 吉富 志津代 氏
活動概要
兵庫県三田市において社会福祉協議会と三田市の国際交流協会が連携する仕組みづくりを行っている。
NPO法人多言語センターFACILには現在、常勤・非常勤を合わせて14人の職員が在籍しており、約23年間、翻訳・通訳を通じた多言語・多文化の関連事業をソーシャルビジネスとして行ってきたところ、現在はおおよそ1億円の事業規模。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
社会福祉士はそもそもコーディネーターであるほか、国家資格になっており、人権意識も持っている。また、アセスメントの技術やコミュニケーション力も高められ、社会制度も知っており、いろいろな関係機関、専門分野につなぐことができる。社会福祉士が異文化に関することや外国人関連の制度、言語を身に付けるのは簡単ではない。
スクールソーシャルワーカーやメディカルソーシャルワーカーと同じように、多文化ソーシャルワーカーというものが社会福祉士の一つのカテゴリーとしてきちんと位置付けられることを目指さなければならない。
自治体国際化協会(CLAIR)
令和5年1月30日開催
一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)
活動概要
自治体国際化協会では、全国市町村国際文化研修所(「JIAM」)と共催で「多文化共生研修」を実施している。
「多文化共生の実践コース」を修了することを要件に 「多文化共生マネージャー」を認定している。本研修は定員 40 名で、計6日間(前後期各3日間)実施される。前期修了後には、研修で学んだ内容を踏まえて、自身の地域での課題や、深く調査したいテーマを選択し、今後どのような方法でその解決を進めていくか等を整理した「研究計画書」を作成してもらう。また、後期修了後には、前期で作成した研修計画書に基づいた調査を通じて、解決策を検討し「課題レポート」にまとめて提出してもらう。後期修了後に作成した課題レポートに関して、多文化共生マネージャーの全国組織である「NPO多文化共生マネージャー全国協議会」に登録されている多文化共生マネージャーのうち、1期生や2期生といった、長い間多文化共生マネージャーとして活躍されている専門家の方に依頼して、二人一組で査読をしてもらい、合格点が得られた者を多文化共生マネージャーとして認定している。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
相談者の多くは、中長期的に日本に在留する方になると想定されるため、人権・権利擁護の観点や、社会福祉制度(各種社会保障、社会福祉、高齢福祉等)に係る知識が必要であり、そのような制度をいかに外国人が受けられるかをきちんと踏まえた上でのアセスメントが必要になる。
相手に伝わる言葉で外国の方にきちんと理解してもらうことが重要であるため、やさしい日本語で対応できる能力が身に付く研修を行ってほしい。
日本国内のどの地域で相談を受けたとしても、外国人が同じレベルの均質的なサービスが受けられるよう、国が責任をもってコーディネーター人材を育成していくことが重要であり、それらを踏まえた上で、研修対象人数や研修科目、受講時間数等を検討するべきである。
養成研修の対象を社会人に限定すると、時間的な制約などから真にコーディネーターになってほしい人材が養成研修を受講できない可能性があるほか、高齢化により福祉等の相談員人材が限られる中で、次世代のコーディネーターのなり手がスムーズに見つからないことも想定される。国家資格を視野に入れるのであれば、担い手の裾野を広げる観点から、学生等も研修の対象とするのが良いのではないか。
国際移住機関(IOM)
令和5年1月30日開催
国際移住機関(IOM)
国際移住機関(IOM) 概要
IOMの相談体制について、IOMの職員は9名で構成されているが、そのうち3名が国内事業に関わっており、相談が来た場合はその3名で連絡を受けている。特に2名がケースワーカーとして、事案にしっかり付いて相談を受ける体制となっている。このように、IOMが支援する場合の相談対応は、ケースワーカーが行っている。
相談者の属性は、多くは非正規に在留している外国人や家族等その関係者であるが、支援団体、行政機関、病院、大使館、弁護士等もあるほか、正規に在留している外国人も含まれる。相談は、IOMサイトに電話番号やメールの問合せ先が載っているため、基本的には、メールか電話で連絡が来ることが多い。また、特定のIOMが行っている事業に関して、例えば人身取引被害者の支援事業や非正規に在留する外国人に対する帰国に関する支援事業である場合には、警察、婦人相談所、入管等から直接連絡を受けることもある。
相談内容については、在留資格に関する相談、日本に残りたい、難民認定申請が認定されないといった内容のほか、難民認定申請が不認定の場合にはカナダやアメリカで難民認定申請を行いたいという内容、日本での生活面に関すること、貧困、病気、学校、子供の学習、DV等に加え、自国に帰りたいという相談も寄せられている。
相談件数に関しては、年間50~60件で、1件当たり何度も繰り返し相談が必要な方もいるほか、多くはIOMの事業に関連する相談ではないため、関係機関を紹介する形で終了するものある。そういった場合は、認定NPO法人難民支援協会(JAR)、社会福祉法人日本国際社会事業団(ISSJ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、カトリック東京国際センター(CTIC)、弁護士事務所や大使館といった機関につなげて終了するケースが多い。
IOMでは官公庁や自治体の職員研修での講義において、IOMの事業やIOMができる支援について案内し、IOMがどのような状況でどのような対応ができるのかを伝えており、年間で約400人の職員がIOMの講義を聴講している。
IOMの職員については、ソーシャルワークをするという前提で、かつ、警察や入管等のコーディネーションに関する業務があるということを前提に、そのようなスキルのある方を募集している。必要とされるスキルは、まず言語がその一つであり、加えてソーシャルワークのバックグラウンドがあること、それがなかったとしても、例えば警察や入管でのバックグラウンドがあるなど得意分野のある方を採用の条件としている。IOMのケースワークを担当している職員は、短期間での入替えは考えておらず、長い方で20年くらい勤務している者もいる。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
相談対応支援においては、アクセスしやすい窓口というものが重要であり、また、相談者のたらい回し等を避けるため、支援部署間や相談対応者間のある程度のネットワークやメカニズムが相談受け入れ側、又はコーディネーター間にあるということも重要である。
予防的支援については、コーディネーターがある程度のネットワークを構築した上でいろいろなところで情報発信をして正しい知識を伝えておけば、予防にも効果的であると考える。
コーディネーターとして求められる方は、言語の問題を含めて多文化の配慮や理解のある方、又はカウンセリングの経験や技術のある方である。2点目として、入管の制度、福祉制度及び介護保険制度など、各種行政制度への知識がある方、さらに関係機関の異なる機能と立場に対する知識の理解と調整能力のある方、問題の所在を確認する多角的視点と判断力のある方というのが挙げられる。
コーディネーターの認証制度について、コーディネーターには幅広い資質が求められることから、研修が修了して認証される研修制度を取ることは選択肢としてはあり得る。ただし、認証に当たって研修受講者や日本語の能力が高い方といった枠が設けられた場合、外国にルーツを持つ方の経験を発揮しようとしても、そうした資格要件等が障害となってしまう場合があり、そうした人材の制度への参入が拒まれる可能性がある。
IOMでは人身取引対策事業を行っているが、人身取引は事案の傾向も対策も、行動計画が定期的に更新されるなど常に状況が変化している。このため、省庁や民間が開催している会議やワークショップ、ミーティング等に積極的に参加することで、常に情報を更新するとともに、IOMの知見や経験を共有するよう努めている。
行政書士会
令和5年2月7日開催
日本行政書士会連合会
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
生活上の困り事を分野ごとに振り分けられる能力が必須である。そのためには、適切な判断を行うための基礎知識・法律の知識が必要となることはもちろんのこと、適切な連携先を選択する能力、コーディネーターに関する理解、企画・設計・マネジメント能力、総合調整能力等を身に付ける必要がある。
コーディネーターは外国人と接する仕事であるため、コミュニケーション能力も当然のことながら重要である。
学科試験だけではなく、コミュニケーション能力や、相談事を分野ごとに振り分けられる能力等が身に付いているかどうかをきちんと見極めるための面接試験を実施するなど、しっかりとしたコーディネート人材となるように考慮してほしい。
国家資格化した結果、各コーディネーターが民間事業のような形で本制度を利用することも想定されるところ、手数料の発生等により外国人が気軽に相談できなくなることも考えられるため、商業的にならないような制度設計をしてほしい。
全ての国家資格において、非常に厳しい試験が設けられていることから、本件コーディネーター制度についても、それに準じた厳しいものにしてほしい。
コーディネーター制度は基本的に認証制度にとどめ、国家資格者がコーディネーターとして認証を受け、各分野で専門性を生かした情報提供を行い、予防的支援を実施するのが良いのではないか。
実際にあった事例として、外国人女性が妊娠した際に、オーバーステイを理由に母子手帳が発行されない事例があった。本件については、行政書士が間に入り、パートナーが住所を置いている自治体に依頼したことで最終的に母子手帳を発行されることとなった。こどもの健康福祉のためにも柔軟に対応するようにしてほしい。
商工会議所
令和5年2月9日開催
日本商工会議所
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
コーディネーターには、相談者に対する直接の対応と予防的な支援を期待する。
相談者への直接の対応に加えて大事なのは予防的支援である。外国人が転入して来た際に、その地域で暮らす上で必要な基礎知識を研修することが大切である。転入時だけでなく、定期的に情報のアップデートを行い、能動的に外国人とコミュニケーションを取ることも非常に大事である。
認証制度を設けることは否定しないが、コーディネーターとしての役割は、国家資格を持っているからできるというものではなく、また、一定の座学を受ければできるというものでもないと考える。コーディネーターとしての役割を果たすために学ぶべき基本的な知識を示す必要があるが、一方で、実際にコーディネーターに類似した活動を行っている方を中心に、事例の共有と問題解決を行っていく仕組み作りを可能な限り早期に始めた方が良い。
弁護士会
令和5年2月17日開催
日本弁護士連合会
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
非正規滞在者を支援の対象に含めることは難しいかもしれないが、非正規滞在者の中には、難民認定申請をしても認められない方や、日本人の配偶者や子供がいる方などもいる。弁護士の立場としては、そのような方にも支援の手を差し伸べる必要があると考えており、非正規滞在者等が困り事を抱えている場合に、弁護士や支援者につなぐための仕組みも検討してほしい。
難民問題に関する相談が今後増えていく可能性があると感じている。人手不足を外国人労働者に頼るという流れが今後も続くことが見込まれるため、労働問題に関する相談が増加すると考えられるほか、日本で生まれたり、日本に来た外国籍の子供の生活や教育に関する相談、日系ブラジル人等の高齢化に関する諸問題の相談も増えると感じている。
外国人の高齢化が進んでいく中で、死後の相続等の相談が寄せられることが考えられるところ、基本的には、相続の法律について、どの国の法律で適用されるかなどのテクニカルな問題に対処できる能力が必要である。他方、偽装結婚の場合の相続問題などについては、対応が難しいと感じている。
教育団体
令和5年2月20日開催
日本語教育機関団体連絡協議会
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
特に必要な能力は、我が国の基本的な社会の制度や法令に関する知識である。
また、重要なのがコミュニケーション能力であり、知識ばかりがあっても相談対応は対人なので、コミュニケーションや意思疎通がしっかりできる方でないと問題がある。
コミュニケーションを取る上で1番良い方法は、母国語でいろいろ話を聞いてあげられることであり、それが困難であっても、媒介語として英語などの語学スキルがあった方が良い。日本語でも構わない場合も多いと思われるが、その際はやさしい日本語で話すスキルを持っている方がコーディネーターであれば、コミュニケーションを取るのに役立つだろうと思われる。
経団連
令和5年2月21日開催
一般社団法人日本経済団体連合会
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
入管法の理解が重要。また外国人の在留状況を正確に把握する能力は必須である。
国家資格化することにより、コーディネーターに求められる能力や研修内容が体系化されるという良い点がある。
コーディネーターを国家資格化する取組みは、諸外国では聞いたことがなく、日本がトップランナーとしての役割を果たせるのではないか。この資格制度を体系化し、グットプラクティスとして日本から発信できるような制度設計になることを期待する。
出入国在留管理庁は外国人の出入国と在留を管理するだけではなく、在留外国人を支援する目的で設置された組織である。このコーディネーター制度が創設された場合には、在留支援に注力していることを国内外に示す良いメッセージになる。
社会福祉士会
令和5年2月22日開催
公益社団法人日本社会福祉士会
活動概要
日本社会福祉士会は、コロナ禍前の 2018 年に、在留外国人総数上位100自治体の各領域で働く福祉専門職を対象に、外国人の相談対応で感じている課題・問題を調査し、「「滞日外国人支援に携わる実務者(社会福祉士)の滞日外国人支援基礎力習得のためのガイドブック作成及び研修プログラムの開発事業」報告書」に取りまとめた。福祉専門職は外国人の相談対応において、①コミュニケーション・言語の問題、②異なる文化、宗教、生活習慣によって相手を理解することや信頼関係構築の難しさ、③外国人が日本の制度を十分に理解していない(日本社会への理解を図ることの難しさ)、④在留資格によって制度や行政サービスが利用できない、⑤外国人支援で連携する機関(外国人を対象に支援する団体等)がない、といった課題意識や問題を抱えていることが明らかとなった。
調査報告書や、当会が厚労省の社会保障審議会に提出した「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる実践能力」で示された「社会福祉士が果たすべき役割」を踏まえた上で、外国人相談において求められる役割や業務内容を検討するに、①より良いコミュニケーションが図れるように、通訳の手配、やさしい日本語での対応、日本語文書の翻訳や、分かりやすい説明をすること、②外国人及びその家族の抱える生活課題やニーズ、強みについて、社会的、心理的、身体的、経済的、文化的側面から把握し分析をすること、③外国人及びその家族の生活課題の解決、ニーズ充足、自立等のための支援計画の作成、実施、点検をすること、④適切な社会資源(行政、福祉関係者、弁護士や司法書士等の専門職、民間支援団体、学校、病院、警察、日本語教室、当事者団体(エスニックグループ)、協会など)につなぐための仲介、調整をすること、⑤外国人及びその家族の権利擁護や、ニーズを自ら表明できない場合に代弁をすることが求められると考えている。
「総合的な支援をコーディネートする人材」に対する意見
人権・差別意識、多様性の尊重、守秘義務等の倫理、援助原理(主体性、自己決定の尊重等)といった価値や倫理観を持っていることが重要であると考えている。知識面として求められるのは、人間理解に関する幅広い知識(福祉、教育、心理、医療等)、社会福祉、生活関連の法制度や行政等各種サービスに関する知識、外国人の受入れや共生施策、入管法や在留資格等の知識、国際移住に関する社会的背景の知識であると考えている。
求められる技術(能力)としては、①相手をより良く理解するためのコミュニケーション能力等の相談面接技術、②生活課題や強みの把握、分析を行い、支援計画を作成し、課題解決を図ったり、自立を促進したりする能力、③人権を擁護し、代弁したり交渉したりする能力、④異なる文化や価値観等を理解し適切に対応する能力(文化的コンピテンス)や、⑤多機関・多職種との連携、ネットワークを図り、外国人を適切な支援へ円滑につなげ、協働で課題解決を図る能力であると考えている。
コーディネーターとして最低限求められる能力は、上記で述べたものであるが、そのほかにも、基盤整備、環境整備のために、①エスニックグループの組織化や支援、②地域の外国人が抱える課題やニーズ、社会資源の把握、分析(地域アセスメント)を行い、地域の外国人の課題解決に向けての体制作りや社会資源の開発をする能力、③外国人との共生社会作りをする能力(外国人と日本人の相互理解促進や啓発活動、地域行事やイベントでの共同作業、外国人の意見を取り入れる会合、共生社会の実現に向けた計画立案など)が求められると考えている。
コーディネーター制度について、単に連携先へのつなぎ業務だけではなく、「本人や家族への直接的な相談支援機能や自立支援機能」や「間接的な外国人との共生社会体制づくりの機能」等の業務を含めるのであれば、高度な専門性が要求されると考えられるところ、社会福祉士は相談援助のプロであることから認証制度で十分であると考えている。
社会福祉士保持者の場合は、上乗せの研修等で「外国人支援の特有な知識・技術(例えば在留資格の知識、文化的コンピテンス、やさしい日本語の活用等)」を学ぶことができると考えている。

在留資格 見積もり は VISAdeAI
在留資格取得にビザ申請の最安値を自動見積もりできます!
お試しください。一番安い報酬額がわかります!