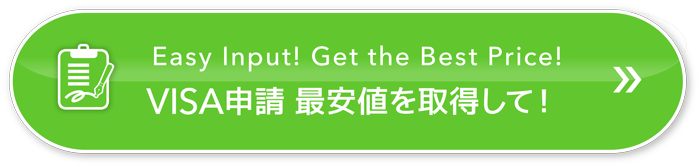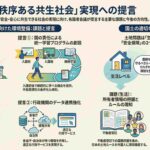2025年10月、出入国在留管理庁は在留資格「 経営・管理 」に関する上陸基準省令等の改正を公表しました(施行日:2025年10月16日)。この改正は、外国人が日本で企業経営を行う際の「質」を問う内容へと大きく舵を切るものです。これまで、形式的な資本金要件や事務所設置だけで 経営管理ビザ 取得を狙うケースも見られ、実質的な経営実態が伴わない申請が問題となっていました。
今回の省令改正では、出資額や経営経験、日本語能力、雇用体制といった「経営の実行力」を重視する方向へと見直されています。日本での事業運営を真剣に行う外国人にとっては歓迎すべき整備であり、行政書士としても新しい基準に即した支援が求められる時代の到来といえます。
改正の経営管理ビザ 全体像:いつから、何が変わるか

今回の改正は、2025年10月16日から施行されます。改正の対象は、外国人が日本で会社を設立し経営する際に必要な在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令です。
改正のポイントは、①出資額などの財務基準の見直し、②経営経験や学歴等の人的要件の追加、③雇用や日本語能力の条件明確化、④事業計画書の実効性確認義務化など、多方面に及びます。
これにより、形式的な要件を満たすだけの申請ではなく、「日本で継続的に事業を運営できる実力」を備えた経営者であることが求められる制度へと進化しました。
参考:出入国在留管理庁
新しい 経営管理ビザ 許可基準の主なポイント
今回の改正では、在留資格「経営・管理」を取得するための要件が、従来よりも明確かつ厳格化されました。形式的な会社設立ではなく、「継続的に経営活動を行う実力を有するか」が審査の中心となります。主な改正ポイントを以下に整理します。
1.出資額・財務基準の見直し
これまでの「資本金500万円以上」という最低要件は、3,000万円に引き上げられました。
2.経営経験・学歴等の人的要件
申請者が「経営を担うに足る能力」を有するかどうかを判断するため、3年以上の経営・管理経験または経営関連分野の学位(修士以上など)を有することが新たに求められます。単なる投資目的ではなく、経営判断や組織運営に関与できる人物であることを証明する必要があります。
3.常勤職員の雇用義務化
従来は経営者1人のみでの事業運営も認められていましたが、今後は少なくとも1名の常勤職員を雇用することが必須となります。さらに、日本人、もしくは、特別永住者などの身分系の在留資格を持つ外国人に限られます。
4.日本語能力の明確化

経営者または主要な管理職が、ビジネス上支障のない日本語能力を有することが条件化されました。目安として日本語能力試験(JLPT)N2レベル以上、またはそれに準ずる日本語運用能力(BJTや大学修了資格等)が想定されています。外国人経営者が日本人顧客・行政機関と円滑に対応できることが重視されます。
5.事業計画書の実効性確認義務
今後の申請では、事業計画書の内容が単なる形式的なものでなく、収支計画・販路・資金繰りなどの実現性を有するかどうかが審査対象になります。
さらに、税理士・中小企業診断士・公認会計士といった専門家による「事前確認」を経ることが義務づけられます。
6.事務所要件の厳格化
自宅兼用オフィスや仮設的な事務所は原則として認められにくくなります。登記上の所在地だけでなく、実際の事業活動が行われているか(机・設備・従業員の勤務実態等)が確認されます。賃貸契約書や現地写真など、物理的実在性の証明が重要です。
これらの変更は、「形式要件の厳格化」というよりも、「実質的な経営者としての信頼性」を問う方向への転換です。真に日本で事業を展開したい外国人経営者にとっては、ビザ制度の信頼性が高まる意義ある改正といえるでしょう。
経過措置・適用時期:移行対応と注意点
改正省令は2025年10月16日に施行されますが、施行日前に提出された申請については、原則として改正前の基準が適用されます。つまり、2025年10月15日までに受理された「経営・管理」ビザ申請は旧要件のもとで審査されます。
ただし、施行日以降に更新申請を行う場合は、原則として新基準に基づく審査が行われます。特に、常勤職員の雇用や日本語能力などの人的要件については、改正後の更新時に確認される可能性が高く、早めの対応が重要です。
なお、実務上は一定の経過措置期間が設けられ、すでに在留中の経営者には緩やかな移行運用が行われる見込みです。
施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断がなされます。
経営管理ビザ 既存保持者・審査中申請者への影響

今回の改正は、施行日以降に新たに申請する者を主な対象としていますが、すでに「経営・管理」の在留資格を持つ経営者にも中長期的な影響があります。
まず、2025年10月15日までに提出された申請は改正前基準で審査されるため、現在申請中の案件は従来通りの取り扱いとなります。ただし、更新申請や在留期間の延長に際しては、新しい基準が段階的に適用される見込みです。
とくに、常勤職員の雇用要件や日本語能力など、人的要件に関する部分は更新審査で確認される可能性が高いため、今のうちに体制整備を進めておくことが重要です。
将来の更新に備えた早期対応こそが、安定した事業継続への鍵となります。
経営管理ビザ 実務対応/準備すべき具体策
今回の改正により、「経営・管理」ビザの審査は、形式要件から実質要件へと大きく比重が移りました。行政書士として支援する立場から、以下の点を早期に整備することが肝要です。
1.出資金の正当性と証拠の確保
資本金や出資金は、送金経路の透明性が問われます。銀行振込記録や送金証明書を保存し、現金持込みや第三者経由の資金調達は避けましょう。税務署や金融機関の確認書を添付することで、資金の信頼性を高められます。
2.常勤職員の雇用体制の整備
今後は実際の雇用関係の存在が重視されます。雇用契約書・給与台帳・社会保険加入証明など、継続的な雇用を示す資料を用意しておくことが必要です。家族や名義貸し従業員ではなく、実態のある雇用であることが求められます。
3.日本語対応力の証明
経営者自身または主要スタッフが日本語で行政・商談を行える体制を示しましょう。日本語能力試験(JLPT N2以上)の合格証明や、日本の大学・専門学校卒業証明があれば効果的です。日常業務のやり取りを日本語で行っている事実を記載することも有効です。
4.事業計画書の専門家確認

今後の審査では「実現可能な事業計画」であることが必須となります。税理士・中小企業診断士・公認会計士などの専門家に内容を確認してもらい、収益計画・販売戦略・費用構造などの合理性を裏付けましょう。
5.事務所・設備の実態整備
自宅兼オフィスは原則不可となるため、独立した事業スペースの確保が重要です。契約書・現地写真・賃貸人の同意書などを整えておきましょう。リモートワーク中心の事業でも、登記上の所在地に事業実態があることを説明する必要があります。
これらの準備を怠ると、改正後の審査では「実態不十分」と判断される恐れがあります。逆に、これらを着実に整備することで、日本での事業経営をより安定させ、在留資格の更新・延長を確実なものにできます。
まとめ:リスクとチャンス、対応戦略
今回の改正は、形式的な起業や実態のない会社設立を排除する一方で、真に日本で事業を行いたい外国人にとっては信頼を得るチャンスでもあります。
リスクとしては、出資金の増額や雇用要件の厳格化により、個人規模の起業家には参入障壁が高まる点が挙げられます。しかし、適切な資本計画・パートナーシップ・専門家連携によってこれを克服すれば、制度上の信頼性を逆に強みにできます。
行政書士は、単なる手続代理を超え、経営計画の実行支援や事後管理まで伴走できる体制を整えることができます。
今回の「経営・管理」在留資格の改正は、日本で本気で事業を展開する外国人にとって、制度の透明性と信頼性を高める重要な一歩です。
当事務所では、最新の制度に対応したビザ申請の自動見積もりシステムを導入しており、最安値での手続費用をすぐに確認できます。
VISAdeAI は、あなたの情報を入力するだけで、在留資格申請取次の最安値を自動的に見積もります。今すぐ試してみましょう!